前回の記事に続き、今回はあまり有名ではない国家を取り上げたいと思います。
増税は国家を支える一方、歴史では重税が国家崩壊を招いたマイナ
ローマ帝国やフランス革命は有名ですが、
この記事では、増税 国家崩壊 マイナー例を5つピックアップ。
エジプトの農民反乱や日本の地方
1. マムルーク朝(14世紀エジプト) 税で潰れたスルタン体制

1250~1517年まで続いたマムルーク朝はエジプトを中心にシリア、ヒジャーズまでを支
14世紀、軍事費と宮廷の奢侈を賄う
歴史家イブン・ハルド
これが農村の
1340年代のペストと相まって民衆の不満が爆発し、地方反乱が頻発。
1517年にオスマン帝国
2. 平安時代末期の日本(12世紀) 荘園税と源平合戦の火種

平安時代末期(1150~1185年)は増税 国家崩壊 日本史のマイナー例の1つかもしれません。
貴族や寺社が荘園(私有地)に重税を課し、
『方丈記』に記された飢饉と税負担で、農民は
この不安定さが源氏・
3. 唐末期の黄巣の乱(9世紀中国) 塩税が招いた大反乱

唐朝(875~884年)の黄巣の乱。
安史の乱後、財政難から塩の専売制を強化し、
これにより庶民は塩の密売に走り
そして遂には黄巣(こうそう)率いる農民反乱が長安を陥落させ、唐朝は壊滅
907年の滅亡は、この重税の傷跡が一因です。
4. ビザンツ帝国のイサウリア朝(8世紀) 税で失った民心

ビザンツ帝国(717~802年)のイサウリア朝。
イスラム侵攻への軍資金のため、レオ3世が農民に重税
厳しい税から逃れるために農民が都市へ流出。
802年、女帝エ
5.ムガル帝国末期(18世紀インド) 農民を圧迫した土地税

ムガル帝国(1707~1857年)は、極端な税が国家崩壊に繋がりました。
領土拡大に熱心だった当時の皇帝アウラングゼーブ帝の死後、地方総督
研究によると税率が収穫の50%超にも達し、農民反乱(例:
経済は停滞し、1757年のプラッシーの
国家崩壊が示す増税の落とし穴
いかがでしたか?エジプトの

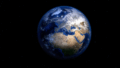
コメント